【初心者向け】ツノガエルの飼育ガイド③ | ツノガエルの病気を予防する方法とは?症状別の早期対処法も紹介
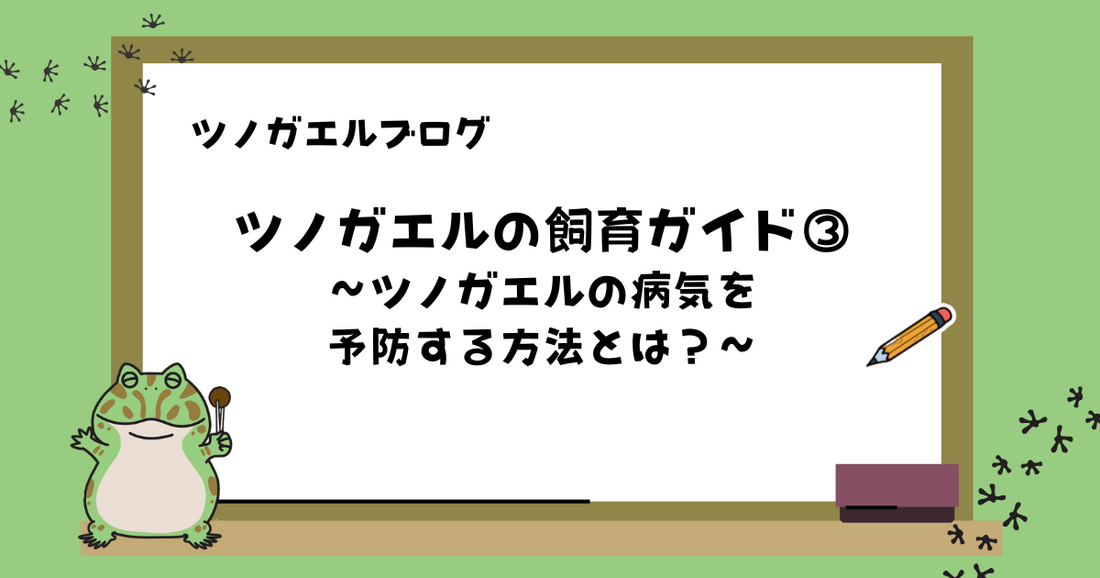
ツノガエルは見た目では体調不良がわかりにくい生き物です。この記事では、初心者にもわかりやすくツノガエルの健康管理の基本や病気の予防法、日々のチェックポイントを解説します。異変の見逃しを防ぎ、ツノガエルと長く付き合うための知識を身につけましょう。
1. ツノガエルの健康状態はどうチェックする?
1-1. 見た目ではわかりにくい?カエル特有の難しさ
1-2. 日々の健康チェックリスト(定量的な観察ポイント)
2. ツノガエルによく見られる病気とその予防
2-1. 肥満(もっとも多い健康トラブル)
2-2. 脱水症状
2-3. 便秘・腸閉塞
2-4. 細菌感染症(レッドレッグ)
3. サプリメントやビタミン剤は必要?
3-1. カルシウム・ビタミンD3の重要性
4. 病気かな?と思ったときの対処法
4-1. 動物病院に連れて行くべきか?
4-2. 飼育者ができる応急対応
5. 急な体調変化を防ぐために
5-1. 急死例の背景にある要因とは?
5-2.「なんとなく元気がない」の放置が危険
5-3. 環境と給餌の一貫性が大切
6. まとめ|健康なツノガエルを育てるために必要なこと
6-1. 環境・食事・観察
6-2. 日々の「なんとなく」をデータ化する大切さ
7. ツノガエルの健康管理についてよくある質問
1. ツノガエルの健康状態はどうチェックする?

ツノガエルは見た目では元気そうに見えても、体の中では異変が起きていることがあります。特に初心者にとっては「じっとしている=健康」と思いがちですが、実はそれが体調不良のサインであることも。毎日の小さな変化を見逃さず、早めに異変に気づくことが大切です。
1-1. 見た目ではわかりにくい?カエル特有の難しさ
ツノガエルは本来、あまり動かない動物です。そのため、「最近あまり動かないから具合が悪いのかな?」と感じても、それが通常の姿であることも。逆に、体調が悪くてもじっとしていることが多いため、見た目だけで判断するのはとても難しいのです。
特に注意したいのは、「いつもより反応が鈍い」「餌に全く興味を示さない」といった変化です。外見は問題なさそうでも、実は腸閉塞を起こしていたケースもあります。些細な違和感を見逃さないことが重要です。
1-2. 日々の健康チェックリスト(定量的な観察ポイント)
ツノガエルの健康を守るために、以下のポイントを毎日チェックしましょう。
| 観察項目 | 正常の状態 | 異常のサイン | 観察のポイント例 |
|---|---|---|---|
| 体型 | 丸みがあり、均等なふくらみがある | 痩せて骨が浮いて見える、または極端に膨らんでいる | 週1回の体重測定や写真記録で比較 |
| 便の状態 | 週1回以上の排便、形がありやや湿っている | 便秘、下痢、細すぎる、異臭、1週間以上出ていない | 床材の上や水入れ内をこまめに確認 |
| 食欲 | 餌にすぐ反応して食いつく | 餌に反応しない、近づけても無視する | ピンセットでの反応を毎回観察 |
| 皮膚の状態 | しっとりとして張りがある | 赤み、ただれ、乾燥、脱皮不全 | 週に1回程度、全身を確認 |
| 目の様子 | 透明で光沢があり、左右対称 | 白濁、腫れ、充血、開きにくい | 給餌時などのアイコンタクト時に確認 |
| 温度・湿度 | 温度:25〜28℃、湿度:60〜80% | 温度変化が激しい、湿度が50%未満または90%以上 | 温湿度計を使って朝晩2回チェック |
これらの観察ポイントを記録しておくことで、異常があった場合に「いつから」「どのくらい変わったか」がすぐにわかります。健康なツノガエルを育てるために、毎日の小さな習慣を大切にしてください。
2. ツノガエルによく見られる病気とその予防

ツノガエルは丈夫な両生類と思われがちですが、飼育環境や餌の与え方によっては、さまざまな病気を引き起こすことがあります。特に見落とされやすいのが、初期症状がほとんど見えない病気です。以下では、よく見られるトラブルとその予防方法を、具体的な観察ポイントとともに解説します。
2-1. 肥満(もっとも多い健康トラブル)
ツノガエルの肥満は非常に多く見られます。原因の多くは、過剰な給餌と運動不足です。ツノガエルは動きが少ないため、餌の量が適切でないとすぐに太ってしまいます。代謝も高くないため、成長期を過ぎた個体には特に注意が必要です。
予防には以下の工夫が効果的です。
・給餌間隔を調整する(成体は週1〜2回が目安)
・定期的に体重を測り記録する
・餌の大きさと種類を見直す
健康的な体型を保つためには、「与えすぎない勇気」も大切です。
2-2. 脱水症状
乾燥に弱いツノガエルにとって、脱水は命に関わる問題です。体にシワが寄ったり、皮膚に張りがなくなったりする場合は、明らかな脱水のサインです。とくに冬場や空調の効いた部屋では注意が必要です。
水場が十分でないケースでは、わずか2日で症状が進行した例もあります。予防には以下を心がけてください。
・ケージ内に常に水入れを設置
・湿度を60〜80%に保つ(湿度計で毎日チェック)
・脱皮の前後は特に湿度管理を強化
肌にうるおいを保つことが、ツノガエルの健康維持につながります。
2-3. 便秘・腸閉塞
ツノガエルは消化不良を起こしやすく、便秘や腸閉塞を引き起こすことがあります。特に、食欲が落ちているときやお腹がふくらんでいるときは注意が必要です。便秘とガスだまりは見た目が似ており、判断が難しいこともあります。
1週間以上排便がない個体を温浴させたところ、その後すぐに大量の便が出たケースがあります。飼育者ができる対策は以下の通りです。
・餌の種類を見直す
・37℃前後のぬるま湯で10分ほどの温浴
・数日間の断食で腸の動きを整える
違和感が続く場合は、獣医師に相談することが大切です。
2-4. 細菌感染症(レッドレッグ)
ツノガエルは、飼育下で細菌感染症(通称「レッドレッグ」)を発症することがあります。特に湿度が高く、不衛生な環境では注意が必要です。この病気は自然界ではあまり見られず、飼育環境との関連が深いとされています。
症状は、四肢や腹部、喉元が赤くただれるほか、潰瘍や出血、食欲不振、腹水、四肢のむくみ、角膜炎、皮膚の剥離など多岐にわたります。放置すると全身に菌が回り、短期間で死亡に至るケースもあります。
飼育者ができる対策は以下の通りです。
・飼育環境を清潔に保つ(糞をしたら床材をすぐに洗浄・交換)
・適切な温度・湿度管理を行う
・レイアウト素材による外傷リスクを減らす
・体調不良が見られた個体は速やかに隔離する
発症してしまった場合は、病原菌に感受性のある抗生物質投与や薬浴(食塩水、抗菌剤溶液)が必要になることがあります。脱水が進行している場合には両生類用リンゲル液での補液が行われることもあります。ただし、自己判断での治療は危険なため、専門の獣医師に相談することが重要です。事前に診察可能な動物病院をリサーチしておくと安心です。
3. サプリメントやビタミン剤は必要?

ツノガエルを健康に育てるためには、餌だけでは不足しがちな栄養素を補うことも大切です。とくに「カルシウム」と「ビタミンD3」の不足は、成長不良や骨の変形といった深刻な症状につながります。飼育下では、自然環境とは違い日光を浴びる機会が少ないため、補助的なサプリメントの活用が推奨されます。
3-1. カルシウム・ビタミンD3の重要性
ツノガエルは、カルシウムが不足すると「クル病」と呼ばれる骨の病気を発症するリスクがあります。特に成長期の若い個体では、骨格形成にカルシウムとビタミンD3が不可欠です。野生下では太陽光からビタミンD3を合成しますが、室内飼育ではUVBライトを使わない限り、その生成ができません。
市販のフードだけでは5大栄養素のうちビタミンとミネラルが不足しやすいということである。これらが長期に不足した場合には、代謝性骨疾患にかかるリスクが高くなる。
代謝性骨疾患には、くる病、栄養性二次性上皮小体機能亢進症、骨軟化症などがあり、イグアナ、トカゲ、ヘビ、ヤモリ、カメ、カエル等あらゆる種類で発症が見られる病気である。
ツノガエルバイトは、こうしたリスクに配慮し、成長と健康維持に必要なカルシウムとビタミンD3を適切なバランスで配合しています。毎日の給餌に取り入れることで、ツノガエルの骨格形成と全身の健康をサポートする設計となっています。
サプリメントを与える場合は、使用量や製品ごとの推奨量は必ず確認してください。健康な体を支えるのは「適量」であることを忘れずに、観察と調整を続けましょう。
4. 病気かな?と思ったときの対処法

ツノガエルに元気がない、食欲がない、動きがおかしい。そんなとき、「様子見」で終わらせてしまうと、取り返しのつかない状態になることがあります。体調の変化には必ず原因があり、早めの対応が命を守る第一歩になります。ここでは、病院に行く判断の目安と、飼育者ができる応急措置について紹介します。
4-1. 動物病院に連れて行くべきか?
まず重要なのは、両生類を診察できる動物病院かどうかです。犬や猫が中心の動物病院では、ツノガエルの病気に対応できない場合が多く、事前の確認が欠かせません。「エキゾチックアニマル対応」や「両生類・爬虫類対応」の表記がある病院を探しましょう。
病院に行く際には、以下の持参物を用意してください。
・便:新鮮なうちにジップロックなど密閉できる袋に入れる(乾燥すると診断が難しくなる)
・餌:与えている餌の種類、量、頻度がわかるように写真やメモを用意
・最近の様子の記録:体調の変化、便の有無、食欲、体重の記録など
「まだ大丈夫かも」と迷った場合も、相談だけでも受けてみることをおすすめします。
4-2. 飼育者ができる応急対応
病院に行く前に、まず飼育環境を見直しましょう。体調不良の原因は、環境ストレスによることが多いため、以下の点をチェックしてください。
・温度、湿度の再確認
・温度は25〜28℃、湿度は60〜80%を保つ
・温湿度計のズレや故障にも注意
・一時的な断食
・餌を与えるのを2〜3日控え、消化器官を休ませる
・その間も水分と湿度はしっかり確保
・ケージ全体の環境チェック
・ 床材の汚れやアンモニア臭はないか
・ 隠れ家や水入れの位置に問題がないか見直す
これらの対応で改善が見られることもありますが、無理に自力で解決しようとせず、異常が続くようなら必ず動物病院を受診してください。飼い主の判断が、ツノガエルの命を左右することを忘れずに行動しましょう。
5. 急な体調変化を防ぐために

ツノガエルは体調の変化を外見に出しにくいため、異変に気づいたときにはすでに深刻な状態に進行していることがあります。急死のリスクを避けるには、日常の観察と環境の安定が欠かせません。「いつもと違う」と感じた瞬間が、対処のタイミングです。
5-1. 急死例の背景にある要因とは?
動物病院に持ち込まれる急死例の多くには、共通点があります。それは「環境の急変」と「栄養の偏り」です。たとえば、エアコンの切り忘れによる低温、床材のアンモニア臭、これらが引き金となって命を落とすケースは少なくありません。
ある飼育者は、急に室温が下がったことに気づかず、翌朝カエルが動かなくなっていたと話してくれました。ツノガエルの体は温度変化に非常に敏感です。人間にとって「少し肌寒い」程度でも、両生類には致命的になることがあります。
5-2.「なんとなく元気がない」の放置が危険
「今日は少し動かないな」「餌に反応が薄い気がする」このような些細な変化を見逃さないことが、健康管理の基本です。
ツノガエルは本能的に弱みを見せない動物です。だからこそ、行動の変化は病気のサインと考え、すぐに記録し、必要であれば専門家に相談しましょう。
5-3. 環境と給餌の一貫性が大切
ツノガエルにとって安定した環境は命綱です。温度、湿度、照明、給餌のタイミング。これらが日によって変わると、ストレスとなり免疫力が落ちます。とくに給餌は、毎回の量や内容を記録し、一定のリズムを保つことが理想です。
おすすめは、以下のような健康記録ノートをつけること。
・体重の変化
・排便の有無と状態
・食べた餌の種類と量
・温湿度の推移(毎日2回以上)
こうした記録は、病気の早期発見だけでなく、動物病院での診察時にも大いに役立ちます。予防は「気づく力」と「記録する習慣」から始まります。小さな異変を見逃さない目を養いましょう。
6. まとめ|健康なツノガエルを育てるために必要なこと

ツノガエルを長く元気に育てるには、「環境」「食事」「観察」という3つの柱がしっかりと支えられていることが大切です。これらはそれぞれ独立しているようでいて、密接に関係しています。ほんのわずかな乱れが、命にかかわる不調につながることもあるため、日々の積み重ねが何よりの予防となります。
6-1. 環境・食事・観察
まず環境は、温度・湿度・清潔さが基本です。温度は25〜28℃、湿度は60〜80%を保ち、床材や水入れの状態を毎日確認してください。次に食事は、餌の種類・量・頻度を適切に保つことが重要です。成体では週1〜2回が目安で、カルシウムやビタミンも必要に応じて補いましょう。
そして観察です。じっとしているツノガエルは、体調不良でも見た目に出にくいため、少しの変化も見逃さない「観察力」が飼育者に求められます。この3つが揃ってこそ、健康な生活が維持されます。
6-2. 日々の「なんとなく」をデータ化する大切さ
「なんとなく元気がない」「昨日より少し動きが少ない気がする」その違和感を言葉や数値にして記録することが、重大な病気の予防につながります。たとえば、
・体重の増減(週1回)
・食欲の有無
・排便の有無と形状
・温湿度の記録(朝・夜)
これらを飼育ノートやスマホアプリで残しておくと、異常の早期発見に役立ちます。大切なのは、日々のあたりまえをなんとなくで終わらせないこと。ツノガエルと向き合う時間が、記録と観察を通じて、信頼と安心に変わっていきます。まずは今日から、記録する習慣を始めてみましょう。
7. ツノガエルの健康管理についてよくある質問

Q. ツノガエルが食べなくなったのは病気?
食欲が落ちた場合、温度や湿度の変化、脱皮前、便秘、内臓の不調などが考えられます。1~2週間程度なら様子見で構いませんが、3週間以上続く場合は病気の可能性があるため、動物病院での診察をおすすめします。
Q. 便が出ていないけど大丈夫?
排便が数日ない場合でも、食事量や環境によっては一時的なこともあります。ただし、腹部がふくらんでいる、食欲がないなどの症状を伴うと腸閉塞の恐れがあります。
Q. 体がふくらんで見えるのは病気?
ツノガエルがふくらんで見えるときは、単なる水分調整である場合もありますが、ガスのたまりや内臓疾患の可能性も考えられます。ふくらみが長時間続く場合や食欲がない場合は、早めの受診が必要です。
Q. レッドレッグ症候群の見分け方は?
レッドレッグ症候群は、手足の裏や腹部が赤くただれたように見えるのが特徴です。皮膚から細菌が侵入し、命にかかわることもあります。湿度が高すぎる環境や汚れた床材が原因となるため、早急な治療が必要です。
Q. ツノガエルの平均寿命は?
ツノガエルの平均寿命は約6〜8年で、10年以上生きる個体もいます。適切な環境管理とバランスの良い餌、定期的な観察が長寿の秘訣です。小さな異変を見逃さず、早めに対処することが重要です。
Q. クル病の症状は?
クル病はカルシウム不足によって起こる骨の病気で、手足が曲がる、動きが鈍くなる、口元が変形するなどの症状が出ます。成長期の若い個体に多く見られ、カルシウムとビタミンD3の適切な補給が予防につながります。
Q. ツノガエルにサプリは必要?
室内飼育では日光不足や栄養の偏りが起きやすいため、カルシウムやビタミンD3のサプリは必要です。ただし過剰に与えると中毒になるおそれもあるため、週1〜2回を目安に適量を守って使いましょう。なお、ツノガエルバイトにはサプリメント追加は不要です。
Q. 目が白くにごっているのはなぜ?
目が白くにごっている場合は、外傷、感染、ビタミンA欠乏、または水質の悪化が原因の可能性があります。悪化すると視力に影響が出るため、環境を見直したうえで、早めに動物病院を受診してください。
Q. 皮膚がむけたけど脱皮なのか病気なのか分からない
皮膚がむけた場合、正常な脱皮であることが多いですが、皮が長く残る、赤みやただれがある場合は脱皮不全や皮膚病の可能性があります。湿度を上げて様子を見て、それでも改善しない場合は受診が必要です。
▶︎参考:田園調布動物病院|カエルの病気
ツノガエルと長く健康に過ごすためには、毎日の観察と適切な環境づくりが欠かせません。この記事の内容を参考にしながら、違和感を見逃さず、毎日の観察から異常を早期に察知しましょう。飼育者の観察力と判断が、命を守る第一歩となります。
エコロギーの品質の「こだわり」について
コオロギの含有率が驚異の「90%」以上
鮮度がいのち。一貫生産と研究体制
早稲田大学や東京農工大学をはじめとする複数の大学と連携し、科学的根拠に基づく研究開発を推進しています。

















