「幻のヤモリ、クレステッドゲッコーが見つかった日」 〜絶滅したと思われていたクレスの知られざる物語〜
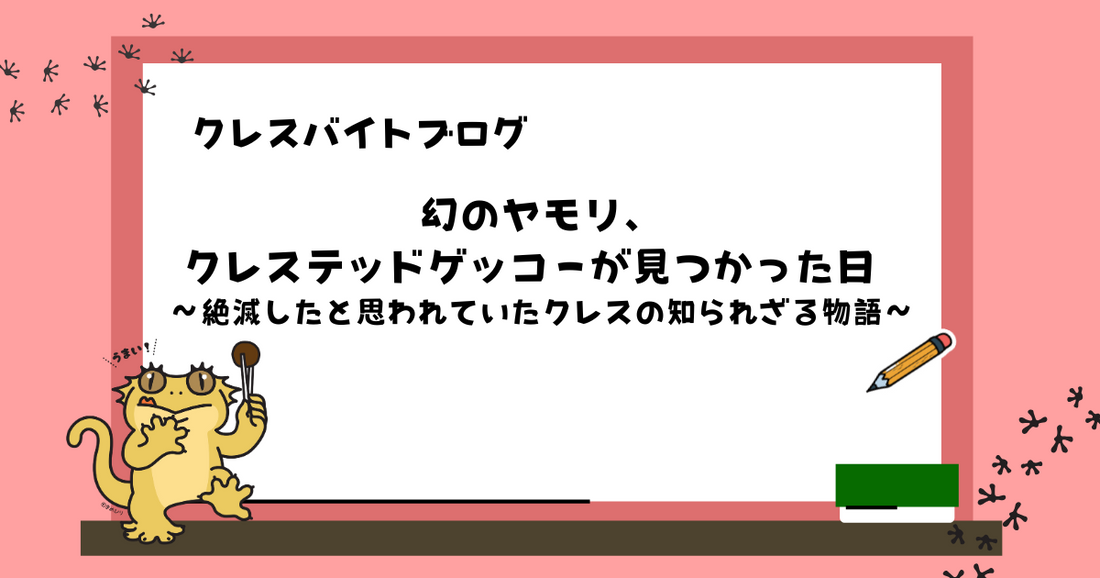
1. 絶滅したヤモリが、今ここにいる
2. クレステッドゲッコーとは?知っておきたい基本情報
2-1. 和名と名前の由来
2-2. 生息地:ニューカレドニアの森
2-3. 習性と身体の特徴
3. クレスが“消えた”100年の空白
3-1. 1866年、最初で最後の記録
3-2. なぜ“消えた”のか?
4. 【転機】1994年、台風が運んだ奇跡
4-1. 倒木の下で見つかった“生きた伝説”
4-2. 繁殖と普及への動き
5. 飼育ブームが保全につながった数少ない例
5-1. CITES II類と人工繁殖の普及
6. クレスの未来を守るために、私たちができること
6-1. 飼育者に求められる3つの意識
7. 【まとめ】「生きる伝説」が、今、あなたの家にいる
7-1. 絶滅と復活、その“物語”の主人公
かつて絶滅したと考えられていたクレステッドゲッコー。しかし、奇跡的に再発見されてからは、ユニークな見た目と飼いやすさから、今では初心者にも人気のペットとして親しまれています。この記事では、クレスの知られざる生態や再発見のストーリーをご紹介します。
1. 絶滅したヤモリが、今ここにいる

現在では爬虫類初心者にもおすすめされる「飼いやすいヤモリ」として親しまれているクレステッドゲッコー(和名:オウカンミカドヤモリ)。その可愛らしい見た目や温和な性格から、ペットショップでもよく見かける存在です。しかし、このヤモリがかつて「絶滅した」と考えられていたことを知る人は、意外と多くありません。
実際、クレステッドゲッコーは19世紀後半に一度だけ記録されたあと、長い間その姿を誰も確認できず、「幻のヤモリ」として分類されてきました。そんな彼らが突如、20世紀末に再び人前に現れたのです。
絶滅とされながらも人の手によって繁殖され、世界中の飼育者のもとで命をつないでいるこの種は、まさに「生きる伝説」と呼ぶにふさわしい存在です。この数奇な運命をたどったクレステッドゲッコーの知られざる物語を紹介していきます。
2. クレステッドゲッコーとは?知っておきたい基本情報

クレステッドゲッコーは、飼いやすくて魅力的な外見を持つことで知られ、今では初心者にも人気のヤモリです。しかし、その特徴をしっかり理解することで、より適切な飼育ができるようになります。ここでは、その基本的な性質や体の構造、生息地について詳しく見ていきます。
2-1. 和名と名前の由来

クレステッドゲッコーの和名は「オウカンミカドヤモリ」。その名の通り、頭から背中にかけて王冠のようなトゲ状の突起が並んでおり、この見た目が「クレス(とさか)」という英名の由来です。この突起は威嚇のためではなく、彼らの進化の名残とも考えられています。
2-2. 生息地:ニューカレドニアの森
彼らのふるさとは、南太平洋のニューカレドニア。特に森林に囲まれた地域に多く生息しています。この島は独自の動植物が多く、隔絶された環境で進化したクレスもその一例です。湿度が高く、樹木が密生するこの地は、クレスにとって理想的な生活空間といえます。
2-3. 習性と身体の特徴

・樹上性:高い場所で過ごすことを好み、地面に降りることは少なめです。
・夜行性:暗くなってから活動し、日中は物陰で静かに休みます。
・雑食性:主に昆虫や果物を食べるため、飼育下では人工フードも活用できます。
・身体構造:まぶたがなく、目を舌でなめて潤します。足には吸盤があり、垂直の壁でも軽々と登れます。
このような性質を踏まえた上で、飼育環境を整えることが重要です。クレスの行動や特徴を知ることで、より深く愛着を持てるはずです。ぜひ彼らの自然な姿を思い描きながら、お世話に取り組んでみてください。
| 性質項目 | 内容 |
|---|---|
| 和名 | オウカンミカドヤモリ |
| 生息地 | ニューカレドニア(独自の生態系) |
| 習性 | 樹上性・夜行性・雑食性 |
| 身体的特徴 | まぶたがない・吸盤で木登りが得意 |
| 名前の由来 | 目の上から背中にかけてのとさか状突起 |
3. クレスが“消えた”100年の空白

現在はペットとして身近な存在となったクレステッドゲッコーですが、かつては「幻のヤモリ」と呼ばれるほど、その存在は長く確認されていませんでした。発見から再発見までの約100年という空白の時間は、爬虫類学の歴史の中でも特異な事例として知られています。
3-1. 1866年、最初で最後の記録
クレステッドゲッコーが最初に記録されたのは1866年。ボヘミア(現在のチェコ)の動物学者が標本として採集したのが最初です。しかし、それ以降の報告は一切なく、生きた個体はどこにも見つかりませんでした。野生での目撃例がなかったため、20世紀初頭には「すでに絶滅した」と判断され、学術的にも姿を消す存在となります。
3-2. なぜ“消えた”のか?
クレスが長らく発見されなかった背景には、ニューカレドニアの地理的・環境的な要因があります。この島は多くの地域が未開発で、山岳地帯や密林には人の手がほとんど入っていません。加えて、夜行性かつ樹上性という特性も、発見の難しさに拍車をかけました。当時の調査技術や研究体制では、こうした隠れた生き物の確認は極めて困難だったのです。
クレステッドゲッコーの100年の沈黙は、単なる「発見されなかった」というだけでなく、生息地や行動特性、調査体制の不備が重なった結果でもあります。この事実を知ることで、野生動物の保護や研究にはどれだけの根気と偶然が関与しているのか、改めて考えさせられます。
4. 【転機】1994年、台風が運んだ奇跡

およそ100年の沈黙を破り、クレステッドゲッコーが再び人前に姿を現したのは1994年。偶然の積み重ねが生んだその瞬間は、爬虫類の歴史を大きく変える出来事となりました。絶滅とされていたヤモリが、自然の力によって再発見されるという「奇跡」は、多くの研究者に衝撃を与えました。
4-1. 倒木の下で見つかった“生きた伝説”
1994年、ニューカレドニアでの調査中、暴風雨の影響で倒れた木の下から、複数のクレステッドゲッコーが発見されました。発見者たちは当初、その姿に目を疑ったといいます。この出来事は、爬虫類学の分野だけでなく、世界中のメディアでも話題となりました。
4-2. 繁殖と普及への動き
この再発見を受けて、欧米のブリーダーや研究者たちが協力し、保護と繁殖に取り組みました。特にアメリカやドイツでは、飼育技術の向上とともに人工繁殖が成功し、現在のペット市場への広がりに繋がっています。この繁殖の進展は、絶滅リスクを抱えた種のモデルケースともされています。
再発見は単なる偶然ではなく、自然と人の関わりが生んだひとつの物語です。こうした背景を知ることは、飼育者としての責任や意識を高める第一歩になります。目の前にいるクレスが「特別な存在」だと改めて実感してみてください。
5. 飼育ブームが保全につながった数少ない例

クレステッドゲッコーは、その飼いやすさと愛らしい姿から世界中で人気を集める一方で、「野生動物の保護」という観点でも注目される存在です。商業的な飼育ブームが、逆に保全活動を後押しするという稀な成功例として評価されています。
5-1. CITES II類と人工繁殖の普及
クレステッドゲッコーは、ワシントン条約(CITES)の附属書IIに分類されており、国際的な取引には一定の規制が設けられています。つまり、本来であれば無計画な輸出入が保護の妨げになる可能性がある種です。しかし、1994年の再発見以降、欧米を中心に人工繁殖の取り組みが急速に進みました。
・人工繁殖の拡大により、現在流通しているクレスのほぼ全てがブリード個体(繁殖個体)となっています。
・野生個体の捕獲需要は事実上ゼロに近づき、自然個体群への影響が最小限に抑えられているのが現状です。
このように、「飼育したい」という需要が、「野生を守る」ことに自然とつながっているのは極めて珍しく、他の爬虫類種ではなかなか見られない現象です。
飼育者がこの背景を理解し、倫理的な繁殖や購入を心がけることで、クレスの保全は今後も持続可能な形で続いていきます。飼うことが守ることになる、この理想的な関係を次世代にもつないでいきましょう。
6. クレスの未来を守るために、私たちができること

クレステッドゲッコーは人工繁殖により安定した流通が実現していますが、野生個体は今もごくわずかです。さらに、生息地であるニューカレドニアでは森林伐採や開発によって環境破壊が進行中です。私たち飼育者一人ひとりの行動が、クレスの長期的な保全に大きく関わっています。(参考:IUCN Red List(Rhacodactylus ciliatus))
6-1. 飼育者に求められる3つの意識
クレスを飼うことは、ただの趣味ではなく「種の存続」にも関わる責任ある行為です。次の3つの行動が、個体の健康はもちろん、種全体の保護につながります。
・責任ある終生飼育
クレスは10年以上生きる個体も多く、途中での放棄は絶対に避けるべきです。生活の変化に左右されず、最後までしっかり面倒を見る覚悟が必要です。
・高品質な人工フードと適切な環境管理
栄養バランスの取れた人工フードを選び、湿度・温度管理を徹底することで、クレス本来の健康を保つことができます。飼育環境の劣化は個体の寿命を縮める要因となるため注意が必要です。
・信頼できるブリーダーやショップからの購入
血統管理や衛生状態がしっかりした環境で育てられた個体を選ぶことは、健全な市場の維持につながります。価格の安さだけで選ぶのではなく、その背景に目を向けることが大切です。
クレスの命を「守る側」に回るには、知識と行動の両方が求められます。小さな飼育環境の中から、大きな保全の輪が広がっていく。そんな意識を持って、日々のお世話に取り組んでいきましょう。
| 行動 | 内容の要約 |
|---|---|
| 終生飼育 | 最後まで面倒を見る覚悟を持ち、途中で手放さない |
| 飼育管理 | 適切な温湿度と人工フードによる健康維持 |
| 購入先の選定 | 血統や衛生管理されたブリーダー・ショップを選ぶ |
7. 【まとめ】「生きる伝説」が、今、あなたの家にいる

クレステッドゲッコーは、単に「かわいいペット」として語られる存在ではありません。一度は絶滅とされた種が、再び人の手によって育まれ、今も多くの飼育者のもとで命をつないでいます。その背景には、数奇な歴史と人との深いつながりがあります。
7-1. 絶滅と復活、その“物語”の主人公
1866年の発見から約1世紀にわたり沈黙を続け、1994年の台風によって“偶然”見つかったクレス。その再発見は、野生動物の保全史の中でも稀有な出来事でした。現在では、人工繁殖によって安定的に供給され、初心者にも手が届く存在になっています。
それでも、野生個体は今も減少傾向にあり、生息地の森林破壊も進行しています。私たちがクレスと向き合う毎日は、そうした現実の上に成り立っているのです。
クレスを飼うということは、単に小さな生き物を育てるだけでなく、「絶滅と再生の歴史の一部を引き継ぐ」ことでもあります。いま目の前にいるその姿が、“生きる伝説”だということを、時折思い出してみてください。そしてその物語を、次につなげていく一人として行動していきましょう。
クレステッドゲッコーはただのペットではなく、絶滅と復活の歴史を生きる存在です。飼うという行為がその保全にもつながる今、私たちができることを改めて考えてみましょう。
エコロギーの品質の「こだわり」について
コオロギの含有率が驚異の「90%」以上
鮮度がいのち。一貫生産と研究体制
早稲田大学や東京農工大学をはじめとする複数の大学と連携し、科学的根拠に基づく研究開発を推進しています。

















