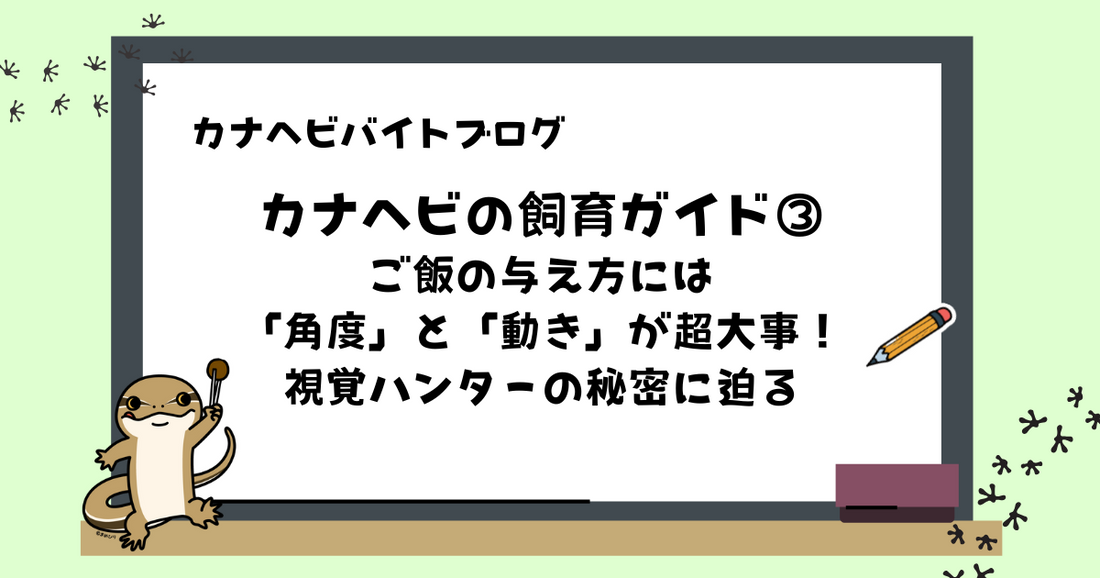初めてカナヘビを家族に迎えたあなたへ
「うちの子、何を食べるの?」
「どうやってごはんをあげたらいいの?」
「もし食べなかったらどうしよう…?」
そんな、ごはんに関するあらゆる疑問を、このガイドがまるごと解決します!
カナヘビの給餌で一番大切なのは、彼らが“動き”で獲物を見つける「視覚型ハンター」だということ。
この記事では、カナヘビがどんなものを食べるのか、そしてどうすれば美味しくごはんを食べてくれるのかを、信頼できる研究結果も交えながら、と〜っても分かりやすく解説していきますね。
目次
カナヘビってどんな生き物?|他の爬虫類との違い
カナヘビ(Takydromus tachydromoides)は、日本のあちこちにある草むらや林でよく見かける、スマートでとっても素早いトカゲの仲間です。
尻尾まで入れると最大25cmくらいになりますが、「体長(鼻先からおしりまで)」は5〜7cmくらいの個体が多いんですよ。
成長具合によって、ごはんのあげ方もちょっとずつ変わってくるのが面白いところです。
- 幼体:卵からかえって半年くらいまでの、小指くらいのサイズの子たち。
- 成体:だいたい1歳以上になって、尻尾まで含めると20cm以上になる大人の子たち。
そして、カナヘビの一番大きな特徴は、なんといっても「視覚」がとっても優れていて、動くものに強く反応する「視覚型ハンター」だということ!
たとえば、ペットとして人気のヒョウモントカゲモドキ(レオパ)は、舌をペロペロ動かして「匂い」で餌を探す「嗅覚型」なんですが、カナヘビは全然違います。
動くものを目でとらえて、一気にパッと捕まえることが多いんです。
2017年の九州大学での研究(Fukudome & Yamawaki, 2017)では、こんな面白いことが分かっています。
カナヘビが獲物を狙うとき、頭を小刻みに何度か動かす「サッカード」っていう動きをするんですが、実は正面じゃなくて、40〜50度くらいの「横目」で獲物を見ているんですって。
これって、「周りの危険をしっかり見つつ、獲物を視界の端っこでとらえて、チャンスと見たらすぐに飛びかかる」っていう、とってもかしこくて洗練された狩りのスタイルなんですね!

どんな餌を食べるの?|おすすめの生き餌・人工餌
🐛 生き餌:自然な本能に合った餌
野生のカナヘビは、クモやいろんな昆虫、小さなムカデ、カタツムリなんかを捕まえて食べています。
お家で飼うときは、次のような生き餌が主によく使われます。
-
コオロギ:
カナヘビのメインのごはんにピッタリ!
タンパク質が豊富で栄養バランスも良く、何よりお家で飼いやすいのがメリットです。
-
ミルワーム:
ちょっと脂肪分が多いので、あげすぎはNG。
おやつとしてたまにあげるのがおすすめです。
-
ワラジムシ・ハサミムシ・クモ:
特に小さめの個体がカナヘビに人気で、赤ちゃんカナヘビのごはんにもぴったりです。
-
チョウやガの幼虫、ムカデの幼体:
もし野外で見つけたら、カナヘビが飛びつくように食べる姿を見られるかもしれません。
2016年の研究(Fukudome & Yamawaki, 2016)では、カナヘビは餌のサイズによって行動が大きく変わることが分かっています。
たとえば…
11~20mmくらいの小さなカマキリには、積極的に飛びついて捕まえようとします。
でも、40mmを超えるような大きな餌になると、頭を振って距離を取ったり、逃げたりする回数が増えるんです。
これは、「食べられそうだけど、ちょっと危ないかも…」って、視覚でリスクを判断していると考えられています。賢いですよね!

🍽 人工フード:「カナヘビバイト」という選択肢
「どうしても生き餌はちょっと苦手…」
「仕事が忙しくて、毎回餌を用意するのが大変!」
そんな方にぜひ知ってほしいのが、カナヘビ専用の人工フード「カナヘビバイト」です。

このフード、とっても優れものなんですよ!
- 昆虫(コオロギ+ミズアブ)由来の動物性たんぱく質を100%使っているので、栄養満点!
- 水で練って与える粉末タイプなので、練り具合で匂いが立ちやすく、カナヘビの食欲をそそります。
- 練り加減を調整すれば、カナヘビの口のサイズに合わせて形や大きさを自由自在に変えられます。
- 常温で保存できるから、長期保管にも便利で助かります。
- カナヘビに必要なビタミンやカルシウムがしっかり添加された総合栄養食です。
食べやすさ、保存のしやすさ、そして栄養バランスのすべてを兼ね備えた「カナヘビバイト」は、忙しい飼い主さんの強い味方になってくれるはず。
そして何より、カナヘビの本能的な嗜好にもしっかり応えるように作られているんです。
餌のサイズ・頻度・与え方の基本
カナヘビの成長段階に合わせて、適切な餌のサイズと頻度を守ることが**健康な成長の鍵**です。
| 年齢 | 頻度 | サイズ | ポイント |
|---|---|---|---|
| 幼体(孵化〜半年) | 毎日 | 頭より小さい虫(5〜10mm) | 成長が早い時期なので、しっかり栄養を与えましょう! |
| 成体(約1歳以降) | 週2〜3回 | 丸呑みできるサイズ(10〜20mm) | 肥満防止のため、運動量を見ながら量を調整してあげてください。 |
餌のサイズは本当に重要です!
カナヘビの頭よりも大きすぎる虫を与えてしまうと、飲み込めなくて喉を詰まらせたり、逆に怖がって逃げ出してしまったりすることがあります。
先ほど紹介したFukudome & Yamawaki(2016)の実験でも、餌のサイズが大きくなるほど、カナヘビが捕まえようとする確率が下がって、逃げる行動が増えることが確認されているんですよ。
無理なく食べられるサイズを選んであげましょう。
---給餌方法の選び方|ピンセットと置き餌の使い分け
カナヘビはとってもデリケートな性格をしています。
時には「人の目が見ている…」などの人の気配で、ご飯にまったく興味を示さなくなることもあるんです。
さらに、冬眠明けや繁殖の時期(春〜初夏)には、特に警戒心が強まって、いつもより慎重になる傾向があります。
だからこそ、「ピンセット給餌」と「置き餌」を状況に応じて上手に使い分けることが、ごはんをしっかり食べてもらうための大切なポイントになります。
✨ ピンセット給餌:動くもので誘惑!
- 餌をピンセットで挟み、カナヘビの目の前でゆっくりと揺らして、動きで興味をひいてあげましょう。
- 餌を差し出す方向は、「正面から」ではなく「横から」がポイントです。カナヘビは横目で獲物をとらえるのが得意だからです。
- ピンセットは、カナヘビを傷つけないように先が丸いタイプを使うと安全です。
🍽 置き餌:そっと置いて様子見
- 警戒心が強い子や、お家にやってきたばかりでまだ環境に慣れていない時期には、置き餌が有効です。
- 小さな餌皿や小皿に乗せて、カナヘビがごはんを食べそうな場所や、視界に入りやすい位置に静かに設置してあげましょう。
- 練り餌タイプ(カナヘビバイトなど)であれば、匂いによる誘導も期待できます。カナヘビが隠れた後に、そっと置いてあげてみましょう。
どちらか一方にこだわるのではなく、カナヘビの気分や季節、その日のコンディションに合わせて補完し合うような使い方が理想的です。