カナヘビの冬眠と冬眠明け完全ガイド 〜失敗しないための準備とケア〜
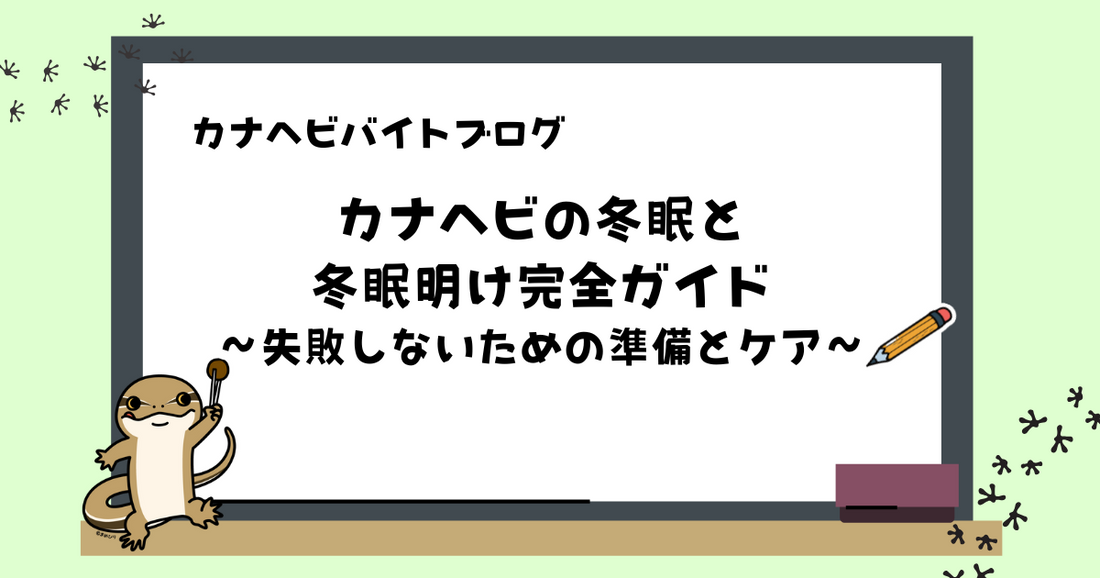
はじめに
カナヘビは野生環境で厳しい寒さを乗り切るために冬眠を行います。飼育下で冬眠を選択する場合は、入念な準備と冬眠明け後の丁寧なケアが不可欠。本記事では、冬眠を成功させるための判断基準と実践手順をまとめて解説します。
1. カナヘビはなぜ冬眠するのか
カナヘビは変温動物で、気温が低下すると活動量と食欲が落ちます。
餌となる昆虫も冬季には激減するため、エネルギー消費を極限まで抑える冬眠が生存戦略として機能します。
2. 飼育下で冬眠させる? させない?
飼育下では冬眠させる方法と加温飼育で冬眠させない方法の二択があります。冬眠は自然に近い反面、準備不足だと死亡リスクが高まるため要注意。
加温飼育を選ぶ場合はケージ内を15 ℃以下にしないよう保温し、活動を維持します。
3. 冬眠を選ぶ場合の準備
- 隠れ家・枯れ葉で暗く静かな環境を用意
- 乾燥を防ぐ水入れの設置
- 風雨を避けられる場所に飼育容器を配置
冬眠準備チェック表
| ステップ | タイミング | ポイント |
|---|---|---|
| 最終給餌 | 冬眠2週間前 | 消化を済ませ、腸内を空にする |
| 温度徐々に低下 | 1週間前から | 日ごとに2〜3 ℃ずつ下げる |
| 環境セット | 前日 | 隠れ家・枯れ葉・水を配置 |
4. 冬眠中の管理ポイント
冬眠中は絶対に刺激を与えないことが鉄則。ケースの移動やハンドリングは避け、必要最小限の確認に留めます。
5. 冬眠明けのタイミングと兆候
最低気温6 ℃・最高気温13 ℃を超える日が続くと目覚めのサイン。
段階的に温度を上げ、急激な変化を避けましょう。
6. 冬眠明け直後の対応
いきなり高温にせず、24時間かけて室温〜24 ℃へ慣らします。こまめに水分補給できる環境を整え、脱水を防ぎます。
7. 冬眠明けの給餌スタート
目覚めから1日後に置き餌を試します。反応が薄くても焦らず、まずは体温の安定を優先。小さめの昆虫や人工飼料から始めましょう。
8. 冬眠明けの注意点
- 体力回復まで単独飼育を徹底
- 無理なハンドリングを避ける
- 環境変化は最小限に
9. カナヘビバイト&レプケア乳酸菌の活用
カナヘビバイトは昆虫100%由来の高嗜好性フードで、冬眠明けの弱った消化器官にも安心。
さらにレプケア乳酸菌を併用すると腸内環境が整い、免疫力アップにも役立ちます。
水を飲まない個体には、浅い水差しに少量まぶして香りで誘うと水分も同時に補給可能です。
まとめ
冬眠はカナヘビの生死を分ける大イベント。今回紹介した準備・管理・給餌のステップを守れば、冬を越えたカナヘビを元気に春へ導けます。ぜひ万全の環境とケアで、新しいシーズンのスタートをサポートしましょう!
エコロギーの品質の「こだわり」について
選ばれる理由 その1
コオロギの含有率が驚異の「90%」以上
コオロギを90~95%(※1)配合した高品質な爬虫類向けフードです。開発段階で含有率50%、75%、95%の3パターンで実験した結果、95%配合の製品が最も優れた食いつきを示すことが判明しました。爬虫類は視覚よりも嗅覚を頼りに餌を認識する性質があるため、昆虫由来の豊かな香りが本能を刺激し、「餌」として認識しやすくなることで自然な捕食行動を促進します。
※1 クレスバイト など、昆虫以外の原料を成長ステージに合わせてバランスよく設計している商品もございます。
選ばれる理由 その2
鮮度がいのち。一貫生産と研究体制
自社一貫生産体制により、収穫から加工までの時間を短縮しています。収穫した後は、すぐに氷締めを行うことで鮮度を維持し、コオロギの香りや風味を保持しています。この工程によって、一般的な昆虫原料と比較して香りが強く、食いつきの良い製品を実現しています。
早稲田大学や東京農工大学をはじめとする複数の大学と連携し、科学的根拠に基づく研究開発を推進しています。
早稲田大学や東京農工大学をはじめとする複数の大学と連携し、科学的根拠に基づく研究開発を推進しています。

















