【特集】レオパの「嗜好性」はなぜこんなに偏る?|餌を探すメカニズムと好き嫌いの原理
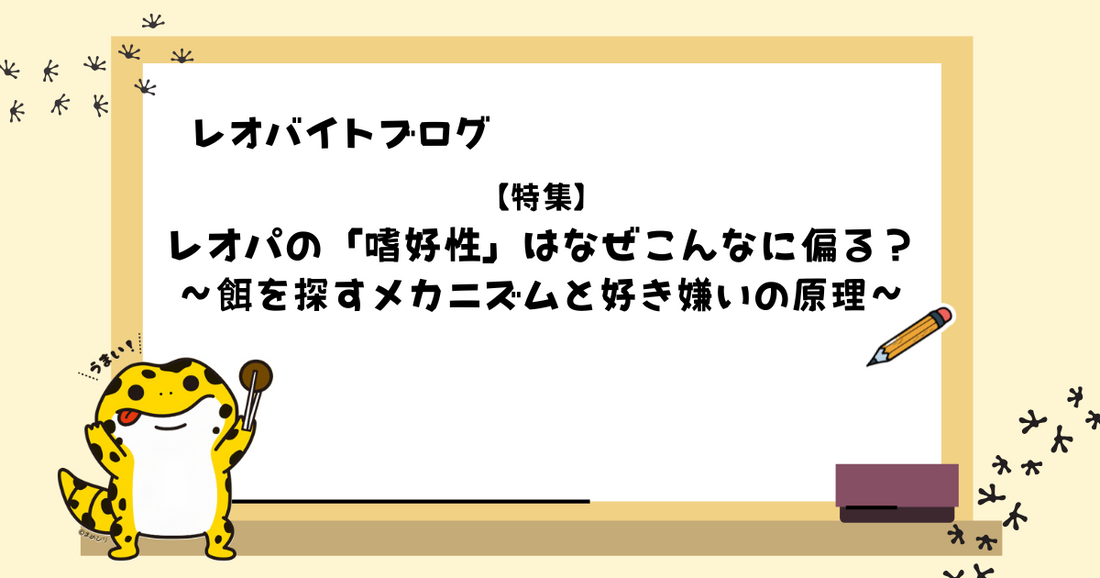
レオパードゲッコー(通称レオパ)は、エサの“好き嫌い”がはっきりしています。
「ハニーワームばかり食べたがる」「人工フードに見向きもしない」──そんな経験、飼育者なら誰しもあるはず。
本記事では、レオパの“嗜好性”がなぜここまで偏るのか、科学的な研究をもとにその仕組みを紐解きます。
目次
- 1. “匂い”で食べるレオパ──舌ペロの秘密
- 2. 一度で“嫌い”を覚える──嫌悪学習と嗜好性
- 3. 積極的な採食者──化学感覚が発達した理由
- 4. 脂質感知とレオパのフード選び
- 5. レオバイト・レオバイトプレミアの高嗜好性の理由
1. “匂い”で食べるレオパ──舌ペロの秘密
レオパは夜行性で、視覚に頼りづらいぶん嗅覚や化学感覚が発達しています。
なかでも「ヤコブソン器官(鋤鼻器)」は、空気中の匂い成分を検知する重要な器官で、レオパはこれを使って食べ物の匂いをキャッチしています。
このとき行われるのが“舌フリック”、通称「舌ペロ」。
不二家のペコちゃん人形のように舌をチロチロ出す姿で、空気中の匂い分子を舌に付着させ、口の中のセンサーへ運ぶための動作です。
実際に何かを給餌する時に、舌ペロを繰り返す姿を見ることが多いと思います。
舌ペロは、餌を探し、食いつくべきものかを確認している作業になります。

2. 一度で“嫌い”を覚える![]() ──嫌悪学習と嗜好性
──嫌悪学習と嗜好性
レオパは、においに対する“嫌悪学習”が非常に強いことが知られています。
たとえば2016年にチェコ共和国で行われたGregorovičováらの実験では、エサにカメムシ由来の防御化学物質(アルデヒド類)を塗布したところ、レオパは強く忌避反応を示しました。
こうした経験は一度で学習され、以後、同様の匂いには近づかなくなります。
この仕組みは、腐敗や毒性のある物質を避けるために重要な能力です。
また、果実や野菜など植物由来のフレーバーにはほとんど反応を示さず、肉食に特化した嗅覚であることも示唆されています。
カメムシのあの特有な匂いは本当に身を守ることに成功しているんですね〜!
3. 積極的な採食者──匂いの感知が発達した理由
レオパは「アクティブ・フォレージング型」と呼ばれる積極的な採食スタイルを持つ爬虫類です。
これは、においを頼りに自ら移動して餌を探す戦略で、待ち伏せ型のトッケイヤモリやヘラオヤモリなどと対照的です。
こうした行動スタイルを持つ爬虫類では、匂いをによる感覚が非常に発達し、においを発生させる餌に対して反応性が高まる傾向にあります。
4. 脂質感知とレオパのフード選び
東京大学のKatoら(2008年)の研究によれば、ヤモリ類の腸管には脂質を感知する受容体(PPARγ)が存在し、食事に含まれる脂質の量に応じて、嗜好行動が変化するとされています。
脂質が多いフードは、よりエネルギー源として効率的であるため、レオパにとっても魅力的に感じられるようです。
実際、脂質が多いハニーワーム(脂質30%以上、乾燥時)は「好きな餌」として扱われることが多く、同じコオロギでも、ヨーロッパイエコオロギ(脂質18〜22%、乾燥時)よりも脂質が多いフタホシコオロギ(脂質20~25%、乾燥時)の方が人気が高い傾向にあります。
ただし、飼育下では脂質のとりすぎは肥満に直結するため、適切な栄養バランスのフード選びが欠かせません。
5. 嗜好性を支えるフード設計──レオバイトの強み
こうした科学的知見をふまえたとき、レオバイトやレオバイトプレミアの高い嗜好性には、明確な理由があります。
まず第一に、コオロギ粉末を90%以上配合しているため、化学感覚を刺激する「においの情報量」が圧倒的に多いこと。これは、嗅覚+鋤鼻器によってにおいを識別するレオパの本能にまっすぐ訴えます。
さらに、魚粉や植物性タンパクを一切使用していないことで、先述のような「嫌悪学習」のきっかけになる異質な匂いを最小限に抑えています。
脂質も重要です。レオバイトやレオバイトプレミアは、嗜好性と健康を両立する適正な脂質バランスで設計されており、代謝的にも受け入れられやすい構成になっています。
一方で、レオバイトダイエットは脂質を意図的に抑え、高タンパク・低脂質設計とすることで、肥満リスクのある個体や代謝が落ちた個体にも対応できる構成になっています。
その分、他2種と比べてやや嗜好性は落ちますが、目的に応じた選択肢が揃っているのがレオバイトシリーズの特徴です。
- レオバイト:嗜好性を重視しつつ、サプリ追加で自由に調整可能なスタンダード設計
- レオバイトプレミア:90%以上のコオロギ粉末+栄養バランスを整えた総合栄養フード
- レオバイトダイエット:脂質を抑えた高タンパク・低脂質設計。体重管理に最適
✅まとめ:レオパの“好み”は科学でできている
レオパのフード嗜好は、「なんとなく」ではありません。
- においを感じる鋤鼻器と舌ペロ
- においと記憶の学習メカニズム
- 脂質を検知する腸の代謝センサー
これらすべてが複雑に絡み合って、「どのフードを食べるか」を決めているのです。
そして、そのすべてのしくみをふまえて設計されたフードが、レオバイトシリーズ。
“ちゃんと食べてくれる安心”の背景には、しっかりとした科学的根拠があるということを、ぜひ知っていただけたらと思います。
📚参考文献
-
Cooper, W.E. & Habegger, J.J. (2000). Lingual and Biting Responses to Food Chemicals by Some Eublepharid and Gekkonid Geckos. Journal of Herpetology, 34(3), 360–368.
-
Gregorovičová, M., & Černíková, A. (2016). Reactions of leopard geckos to defensive secretion of Graphosoma lineatum. Ethology Ecology & Evolution, 28(4), 367–384.
-
Kato, K., Oka, Y., & Park, M.K. (2008). Identification and Expression Analysis of Peroxisome Proliferator-Activated Receptors cDNA in a Reptile, the Leopard Gecko. Zoological Science, 25(5), 492–502.(神戸大学 理学研究科)
エコロギーの品質の「こだわり」について
コオロギの含有率が驚異の「90%」以上
鮮度がいのち。一貫生産と研究体制
早稲田大学や東京農工大学をはじめとする複数の大学と連携し、科学的根拠に基づく研究開発を推進しています。


















